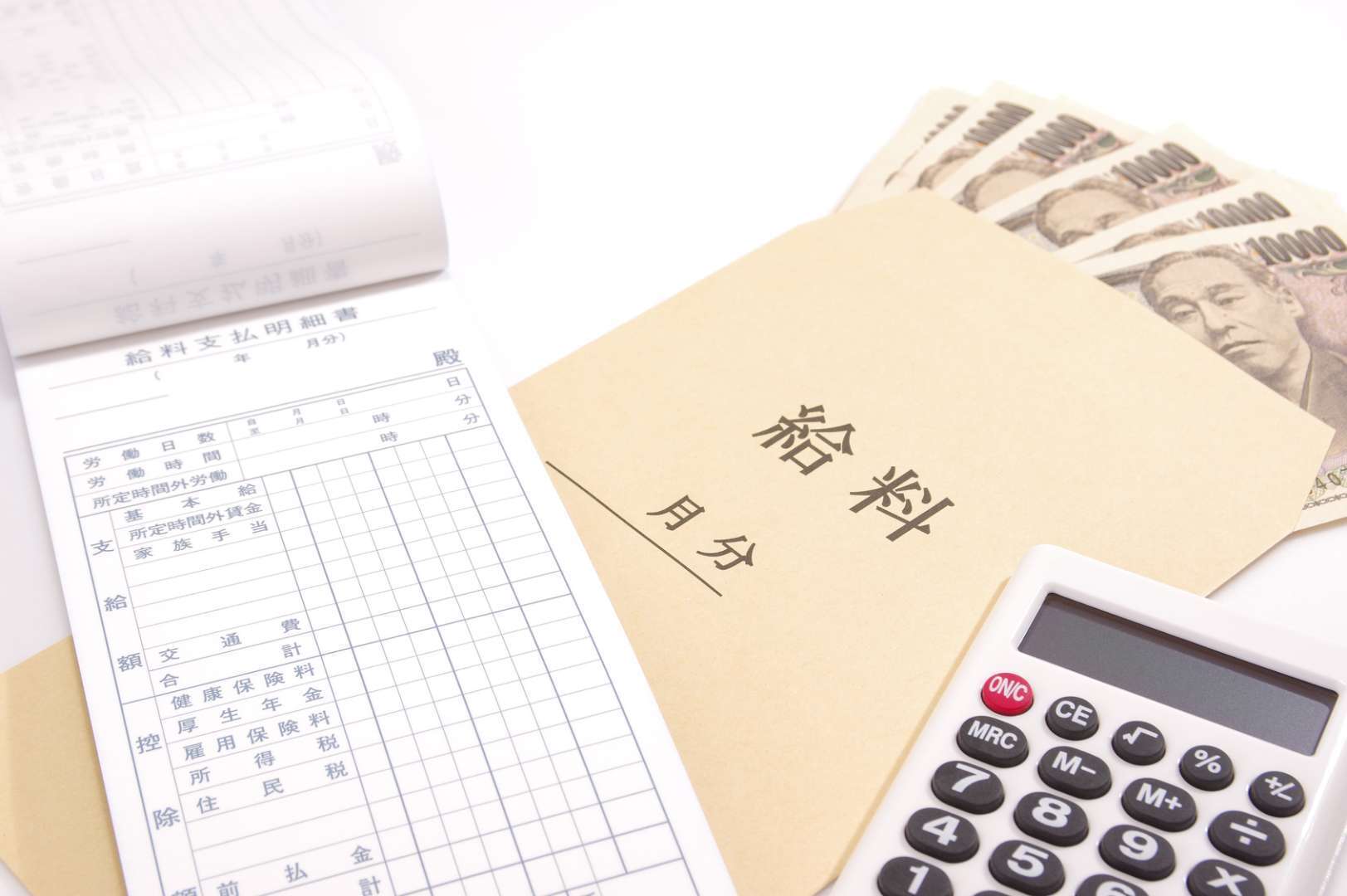「保温屋って、どんな仕事をしてるの?」。そう聞かれても、明確に答えられる人は少ないかもしれません。建設現場では大工や電気工、配管工といった職種がよく知られていますが、保温工事という専門分野は、まだまだ一般的な認知が高くありません。
保温屋は、建物内の配管やダクトに断熱材を巻きつけたり、保冷・防露の処理を施したりする職人です。空調・給排水・プラント設備など、多種多様な配管が張り巡らされた建物のなかで、温度管理やエネルギー効率を保つために欠かせない存在です。見えない場所にあるからこそ、目立ちはしませんが、現代の建築設備においては必要不可欠な工程となっています。
つまり、保温屋は単なる“力仕事”ではなく、専門性の高い施工を担う職種です。そのうえで「儲かるかどうか」を考えるには、まずこの役割を正しく理解することが出発点になります。
月収・年収のリアルと、収入の上がり方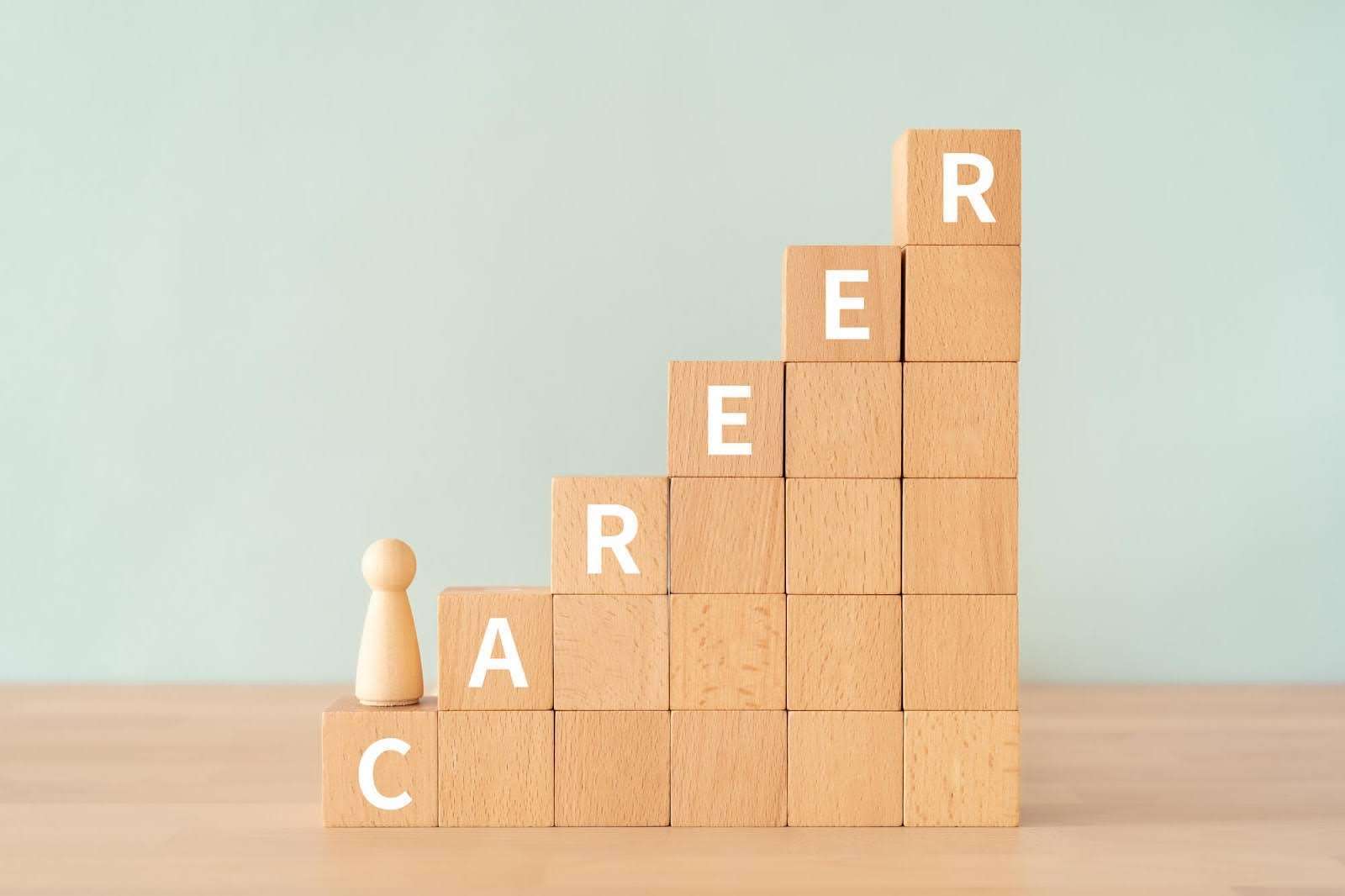
保温屋の年収は、未経験の見習い時代からベテラン職人、そして独立後の一人親方に至るまで、段階ごとにかなり幅があります。たとえば、見習いとして入社したばかりの頃は、月給20万円前後からのスタートが一般的です。これは地域や企業によって差はありますが、他の建設系職種と大きな違いはありません。
ただし、施工スピードや段取り、仕上がりの丁寧さなどが身につくと、徐々に任される作業の幅が広がり、手当や昇給に反映されていきます。早ければ入社2〜3年で月給25〜30万円程度に達することも珍しくなく、賞与や資格手当などが加われば、年収400万円前後まで伸びるケースもあります。
一方で、職長や現場リーダーとして段取りを任される立場になると、責任も増えるぶん収入も上がります。現場をまとめながら複数の職人を管理するような立場では、年収500〜600万円に届くこともあり、さらに元請けとの関係性が良ければ、安定した案件受注も見込めるようになります。
「儲かるかどうか」は、その人がどこまで成長したか、どこまで任されているかによって変わります。収入面だけを見れば派手さはないかもしれませんが、確実にステップアップできる環境が整っているのが保温屋の特徴です。
技術だけじゃない?差がつくポイントはここ
保温屋として収入を伸ばしていくには、単に作業が上手なだけでは足りません。同じ現場に入っても、早い段階で評価される人と、なかなか伸び悩む人がいるのはなぜか。それは、技術と同じくらい「仕事への向き合い方」や「人との接し方」が影響するからです。
たとえば、段取りを読んで自分から先回りできる人は、現場全体の流れを止めません。上司や元請けの信頼も得やすく、自然と「次もお願いしたい」と思われます。また、時間内に丁寧に仕上げる力だけでなく、限られた条件のなかでどう工夫するか、どうミスを防ぐかといった“現場力”があるかどうかも重要です。
さらに、他職との連携が必要な場面では、挨拶や報連相がきちんとできるかどうかが意外と見られます。「この人は現場で安心して任せられる」と思われることが、継続的な仕事や収入アップにつながっていきます。
つまり、保温屋で「儲けている人」は、技術と同じくらい現場の信頼を得ている人です。作業の巧さだけではなく、全体を見て動ける人こそが、安定した収入と成長の両方を手に入れているのです。
「儲けたい」なら知っておきたいリスクと覚悟
「もっと稼ぎたい」と思ったとき、保温屋として一人親方になる、あるいは独立して会社を構えるという選択肢があります。実際、経験を積んでから独立し、自分のペースで仕事を受けるスタイルに憧れる人は少なくありません。ただし、「儲かる」という側面だけを見て判断すると、思わぬ落とし穴にはまることもあります。
まず、独立すれば収入の上限がなくなる一方で、安定は保証されません。元請けとの関係づくり、仕事の受注、材料の仕入れ、人件費の管理、すべてを自分でやりくりする必要が出てきます。施工技術とはまったく別のスキル——つまり、経営者としての視点が求められるのです。
とくに注意したいのは、最初から多くの案件を抱えすぎること。人手が足りず、工期に追われ、品質を保てないと信頼を失い、次の仕事につながりません。また、天候や景気による変動も受けやすく、繁忙期と閑散期の波が大きい年もあります。個人での資金繰りや営業努力が必要になる点は、会社員時代とは大きく異なります。
一方で、うまく波に乗れば月収がサラリーマン時代の2倍以上になることもあります。とくに同業とのネットワークを活かして、応援業務や下請け業務を柔軟に組み合わせられる人は、仕事を切らさず安定収入を築きやすい傾向があります。
つまり、「儲けたい」という気持ちはきっかけにはなりますが、独立後は“職人”であると同時に“経営者”でもあるという現実を受け止められるかどうかが分かれ道になります。勢いだけでは続きません。だからこそ、今の現場で地道に信頼を積み重ねながら、必要な力を一つずつ身につける準備期間が大切なのです。
何年かかる?どう動けば伸びる?現実的なキャリアパス
未経験から保温屋の道に入った場合、「どれくらいで稼げるようになるのか?」というのは誰しも気になるところでしょう。答えは人それぞれですが、目安として3年がひとつの節目です。最初の1年で基本的な作業に慣れ、2年目で作業の流れを掴み、3年目には段取りや仕上げまで任されるようになってくる、というのが一般的な成長カーブです。
もちろん、年数だけで収入が自動的に上がるわけではありません。日々の現場での積み重ね——たとえば、失敗を引きずらずに学びに変えたり、他職と円滑に連携できるよう心がけたり、そうした地道な姿勢が周囲に信頼される人材へと育ててくれます。信頼が生まれれば、「次の現場も頼むよ」と声がかかり、安定した仕事と収入につながっていくのです。
また、資格取得もキャリアアップのひとつの武器になります。たとえば「熱絶縁施工技能士」の資格は、現場での技術力を客観的に証明するものであり、手当や現場選定の優遇につながることもあります。さらに経験を積めば、施工管理側や現場を統括する立場への道も開けてきます。職長としての役割や、工程管理・品質管理まで担えるようになれば、収入の幅はぐっと広がります。
近年では、育成体制や資格支援に力を入れる企業も増えており、やる気のある人にとっては非常に良い環境が整いつつあります。だからこそ、「どの会社で、どんな人たちと働くか」がキャリアに大きく影響します。日々の現場を単なる作業の繰り返しにせず、成長の場として活かせるかどうかが、将来の収入にも直結してくるのです。
保温屋としての未来を考えるなら、どんな働き方が自分に合っているか、一度じっくり考えてみてください。
👉 https://www.minamoto-kogyo.jp/workstyle
安易に稼げると思わないでほしい。でも、道はある
保温屋の仕事は、決して「楽に儲かる」職種ではありません。ただ、コツコツと経験を積み、現場の信頼を得ながら自分の力を磨いていけば、しっかりと生活できるだけの収入を手に入れることは十分に可能です。派手さはなくても、地に足のついた稼ぎ方ができる仕事だというのが、現場で長く働いている人たちの共通した実感です。
「儲かるかどうか」は、結局のところ、自分がどれだけ向き合えるかにかかっています。だからこそ、情報だけで判断せず、まずは現場の空気や人を知ってみることから始めてみてもいいかもしれません。無理なく続けられる環境と出会えるかどうかが、将来の安定に直結するのです。
気になることがあれば、いつでもご相談いただけます。